doi : 10.15027/da4119
初等科音楽 二
| ライセンス種類 |
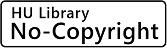
このコンテンツは「パブリックドメイン」の条件で利用できます。詳細はリンク先をご確認ください。|Content is available under the terms of "Public Domain". Check the link for details.
|
|---|---|
| ライセンスURI | https://dc.lib.hiroshima-u.ac.jp/da/page/license1 |
| 所有機関等 | 広島大学 |
| タイトル | 初等科音楽 二 |
| タイトルヨミ | ショトウカ オンガク |
| 著者 | 文部省(モンブショウ) |
| 出版年 | 1942, 昭和17 |
| 出版者 | 大日本図書 |
| 出版地 | 東京 |
| 物理サイズ | 21×15cm, 78p |
| 所在 | 広島大学図書館 |
| コレクション | 教科書コレクション |
| 説明1 | [時期]国定教科書期 1903(明治36年)~1945(昭和20年) [学科]音楽・唱歌 [学校制度]国民学校(昭和16~20年) |
| 説明2 | [解題]『初等科音楽』は『ウタノホン』に続く国民学校初等科用の教科書である。『初等科音楽』1~4は、それぞれ初等科第3学年~第6学年用として昭和17~18(1942~1943)年に出版された。 従前の教科書との違いは、聴音練習や楽典を導入したこと、合唱曲を収録したことで、これにより学校音楽教育の内容が拡充された。『初等科音楽』1には《軍旗》、《三勇士》等の三部合唱曲が含まれている。また『初等科音楽』2からは嬰・変記号や派生音の使用も確認できる。 『ウタノホン』は挿絵が色刷りで比較的児童に親しみやすいものであったのに対し、『初等科音楽』はカラー印刷箇所がなくなった。教科書にも物資の欠乏や戦時体制の強化が顕著にあらわれている。 太平洋戦争前から戦後にかけて音楽教科書が変容した事例として歌詞の改作を挙げることができる。《春の小川》(『初等科音楽』1)や《村の鍛冶屋》(『初等科音楽』2)は詞の一部が削除され、多くの語句が変更された。修正理由は、文語体から口語体への改変、難解な語句から平易な語句への変換、軍国主義的用語の訂正などであった。戦前から戦後の音楽教育の変遷を辿ることのできる重要な教科書である。(解題執筆:仲辻 真帆) |
| 資料番号 | [登録ID]0130449416 [スリップ番号]41015 [請求記号]教科書文庫/4/760/33-1942/0130449416 |

 IIIF Curation Viewer
IIIF Curation Viewer Universal Viewer
Universal Viewer Mirador
Mirador